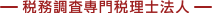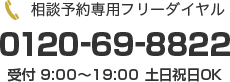NEWS
税務調査の日数は1日で終わる?何時までかかるのかや早く終わるケースを解説
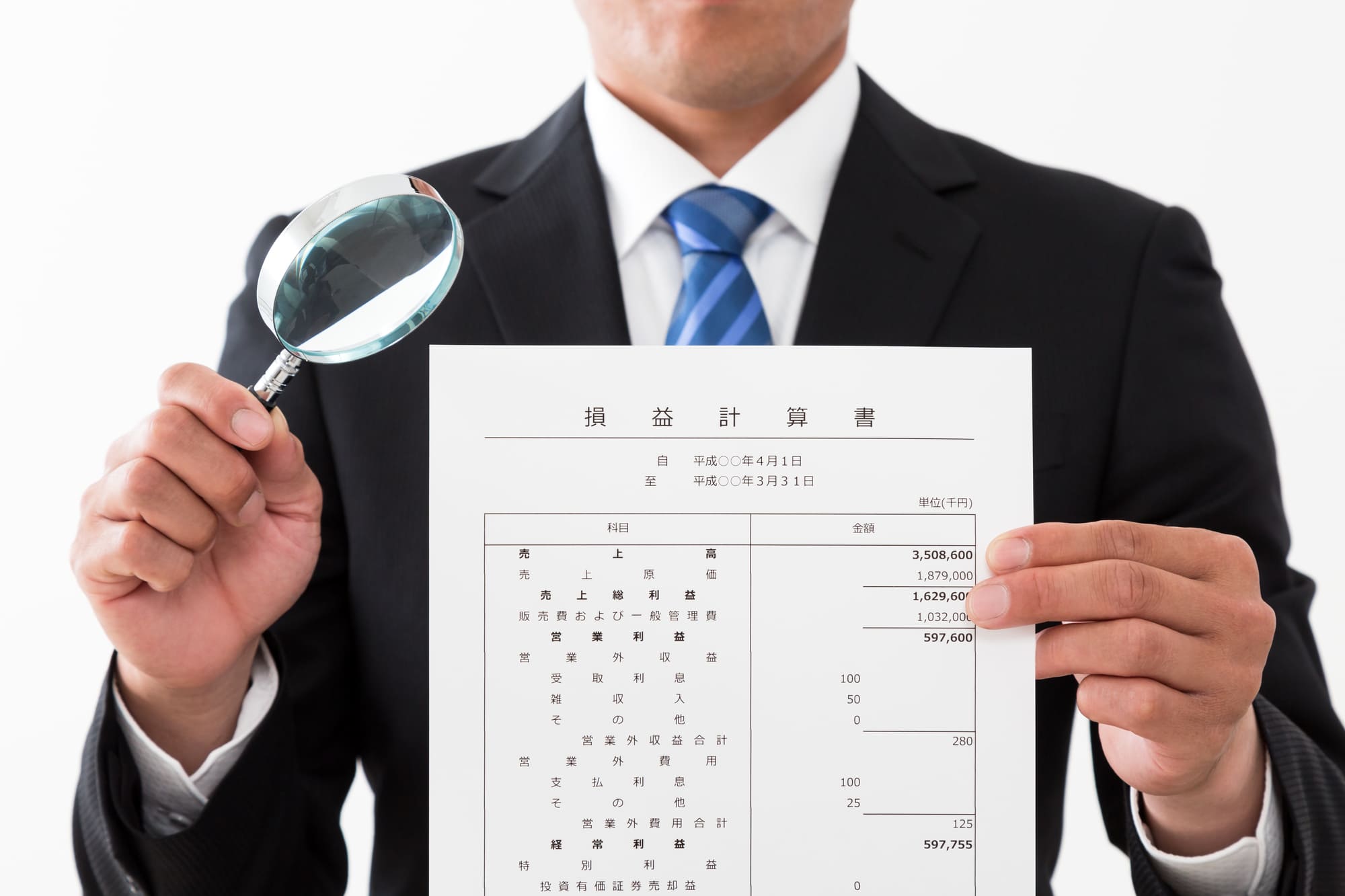
税務調査がやって来ることとなった場合、調査にはどのくらいの日数がかかることとなるのでしょうか。 1日で終わるのか、半日で終わる場合はあるのか、何日もかかるのか、何時ごろまで調査が続くのかなど、気になる方は多いのではないでしょうか。 この記事では、税務調査にかかる日数や早く終わるケース、逆に長くなるケースなどについてわかりやすく解説しています。税務調査となった場合にどの程度の日数を想定するべきなのか知りたい際や、税務調査の流れをイメージしたい際の参考にしてみてください。
税務調査にかかる日数
まずは、税務調査にかかる日数について見ていきましょう。税務調査の日数は法人と個人で異なる場合がある
一般的に、税務調査にかかる日数は2~3日程度と言われていますが、個人事業主と法人とでは若干異なる場合が多いようです。 ケースによっても異なるため一概には言えませんが、個人事業主の場合はほぼ1日、法人の場合2日はかかるのが一般的です。 調査官が事務所などで調査を行う実地調査に1~3日程度、調査後の結果が出るまでにかかる日数は原則3ヵ月以内が目安となります。税務調査の日数について特に決まっている訳ではない
上記で挙げた日数はあくまでも目安であり、実のところ税務調査にかかる日数を税務署や国税庁が発表している訳ではありません。 そのため、調査が半日で終わるケースもあれば、3日以上かかる可能性もゼロではありません。結果が出るまでの日数についても、調査に入ってみるまでは判断できないことも多く、長い場合には1年程かかるケースもあります。 税務調査の日数に決まりはないことを踏まえた上で、早く終わるケースや長引くケースについて、以下で更に詳しく見ていきましょう。税務調査が早く終わるケースはある?
税務調査が早く終わるケースについて解説します。税理士が関与した場合は早く終わりやすい
税務調査は、税理士へ依頼しなくても対応することは可能ですが、税理士が関与している方が早く終わりやすいでしょう。税理士が関与した上で、事前に修正申告を行っている場合、法人の税務調査でも半日で終わるケースも少なくないのです。 税務調査の流れとして ・1日目午前:ヒアリング ・1日目午後から2日目以降:書類、帳簿、データ等の確認業務 となるのが一般的です。 税理士が関与して業務内容や取引先、売上や経費に関する質問などについて明確に説明することができれば、1日目午後からの確認業務が短縮されるケースもあります。 事前の修正申告が必要かどうかはケースによっても異なるため、不安な場合は税務調査対応を依頼する税理士へ確認するとよいでしょう。ミスや間違いがなく、見やすく整理されている
事前通知を受けてから調査当日までに提示できる書類を揃えて、月別に見やすい状態でファイリングする、過去の申告内容を見直して不明な点を説明できるように準備しておく、調査当日には質問された内容に的確に答え、不正が疑われる場合は毅然と説明するなど、調査に協力的な態度を取ることでも早く終わりやすくなります。 税理士が関与した場合に調査が早く終わるのも、調査の際に聞かれやすいポイントを押さえて対応できる点も理由として挙げられるでしょう。 税務調査では「この経費がここから急に増えているのは何故ですか」「この外注先とはどのような関係ですか」といった、一見意図がわからないような質問を受ける場合もあります。 悪いことはしていないのに焦って言葉に詰まったり、うまく説明できずに曖昧な態度を取ってしまうと怪しまれたり、何か隠しているのでは、と更に疑いが強まる可能性があるため、自信を持って対応することも大切となります。無申告や書類がない場合も早く終わる
疑わしいポイントが少ない場合に税務調査が早く終わるケースは多いですが、逆に全く申告をしていない無申告状態の場合や、請求書や領収書、帳簿類などが保管されておれず、調べようがない場合も税務調査は早く終わるでしょう。ただし、この場合重い追徴課税などのペナルティからは逃れられないこととなります。税務調査が長くなるケース
税務調査が長くなるケースについても解説します。以下のようなケースでは、税務調査にかかる日数や結果が出るまでの期間が長引きがちです。多額の不正が疑われる場合
税務調査で多数の不正が疑われる場合、調査するべきポイントが増えていくため、税務調査の日数は長くなってしまいます。 税務調査となる場合、一般的には事前に通知を受ける任意調査であることが多いものですが、事前通知の時点である程度の不正が疑われている、いわゆる「ウラが取れている」状態の場合もあれば、調査に入ってから疑いが強まり、想定よりも調査日数が長引く場合もあります。無申告で資料が多く残っている場合
無申告で資料も保存されていない場合の調査は早く終わりますが、無申告状態で資料がたくさんある場合は、何年分もの資料を細かくチェックする必要があるため、調査にかかる時間も長くなるでしょう。資料を確認しながら質疑応答を行い、新たな疑いが出ればまた指摘される、といった状況の場合、個人への税務調査でも1日で終わらない可能性があります。 ▼税務調査が長引くケースについて詳しく知りたい方はこちら▼ 税務調査が長引くケースと長期化させないための対策計算ミス、記帳漏れが多数ある場合
税務調査でチェックする帳簿や書類に計算ミスや記帳漏れが多数見つかった場合も、調査期間は長引きます。 計算ミスや計上する科目の間違いなど、故意ではないミスであっても過少申告があれば免れることはできませんが、ミスが多過ぎる場合には、故意ではないのに意図的に脱税しようとした疑いを持たれる可能性があるため要注意です。 ミスや間違いが多かったり、必要な資料が不足していたりすると、申告をずさんにしていると受け取られる可能性が高まります。 帳簿管理や申告業務を任せられる経理担当者がいない場合、多忙で申告内容をチェックする時間がない場合には、経理業務全般の代行が可能な税理士事務所へ依頼することをおすすめします。税務調査を早く終わらせたい場合は税理士へ対応を依頼しよう
税務調査は、税制のプロである税理士が関与することで早く終わらせやすくなります。「税務調査が来ても対応できない」「調査が長引くと営業に支障が出る」といった不安や悩みがある場合は、早い段階で税務調査への対応実績が豊富な税理士へ相談しましょう。 税理士法人松本では、元国税OBを含む税務調査に特化した税理士が、個別の状況に応じて丁寧にサポートいたします。現在顧問の税理士がいる場合のセカンドオピニオンや、経理業務の代行、経営コンサルティングなどの相談にも対応していますので、不安や悩みは1人で抱えず、一度お気軽にご連絡ください。まとめ
税務調査の日数が何日かかるのかについて、国税庁が明確にしている訳ではないものの、個人は1日、法人は2日、長くても3日で終わることが多いようです。多数のミスや不正が発覚したり、無申告で書類が多かったりする場合には調査期間は長引きますが、税理士が関与することで早く終わらせやすくなります。また、調査後の結果が出るまでの期間は3ヵ月から、長ければ1年程度を要します。 しっかりと準備して、適正な申告が守られていれば、税務調査は必要以上に怖がるものではありません。経験豊富な税理士のサポートなども検討して、税務調査を乗り切っていきましょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
仮想通貨は税務調査でいくらから指摘される?申告が必要な取引も解説!

近年投資の商材として注目されている仮想通貨は、いくらから税務調査で指摘される可能性があるのでしょうか。仮想通貨を購入した時点で申告が必要なのか、どのタイミングで課税対象となるのかについても気になるところです。 この記事では、仮想通貨に税金がかかるタイミングや確定申告が必要となるケース、申告しなかった場合の事例などについてわかりやすく解説しています。仮想通貨の収入と税務調査について知りたい際の参考としてお役立てください。
仮想通貨に税金がかかるタイミング
仮想通貨(暗号資産)に税金がかかるタイミングについて解説します。仮想通貨を持っているだけでは課税されることはない
結論から言うと、仮想通貨を保有しているだけでは、課税対象となることはありません。仮想通貨を売却して相当額の日本円を得たり、仮想通貨を決済に使用したりしたとしても、保有した時より価格が下がった状態であれば利益は出ていないため、原則として申告は不要となります。仮想通貨が課税対象となるタイミング
仮想通貨が課税対象となるタイミングは以下の通りです。 ・仮想通貨の売却 ・他の仮想通貨への交換 ・仮想通貨による決済 ・仮想通貨の無償受け取り ・商品やサービスの対価として仮想通貨を受け取った時 ・仮想通貨のマイニングやレンディング(貸出)などで利子を得た時 仮想通貨を購入した時よりも価格が上がった状態で売却すると、その時点で利益が確定することとなり、購入時と売却時の差額は課税対象となります。 購入時よりも価格が上がった状態で別の仮想通貨へ交換したり、決済手段に使用したりした場合も、購入当初より高いレートで使用できた場合は課税対象です。 無償で受け取った場合や、商品、サービスの対価として仮想通貨を受け取った場合、仮想通貨のマイニングによる取得や貸出による利子の受け取りなども課税対象となります。 日本円を得ていなくても、無償で仮想通貨を入手した場合や、仮想通貨による交換、決済に使用した場合は課税対象となる点に注意が必要です。 ただし、売却益が出ていても確定申告の必要がないケースもあります。仮想通貨で確定申告が必要となるケース
仮想通貨で確定申告が必要なケースについて解説します。仮想通貨の所得が20万円を超えた場合
仮想通貨による所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、仮想通貨の売却益が21万あった場合でも、売却や送金にかかった手数料が1万円以上ある場合、所得は20万円を超えないため確定申告は不要になります。(学生や主婦の場合)仮想通貨の所得と他の所得が年間48万円を超えた場合
学生や主婦、無職の方の場合、扶養枠である年間所得48万円を超えた場合には確定申告が必要です。他に事業所得がある場合
仮想通貨の所得が20万円を超えていなくても、他の事業所得と合算して20万円を超える場合には、仮想通貨の所得と併せて確定申告しなければなりません。 また、仮想通貨の所得と事業所得の合算が20万円に満たない場合でも、次のケースでは確定申告が必要です。 ・個人事業主として毎年確定申告をしている ・事業年度の途中で会社を退職し、年末調整をしていない場合贈与の控除額を超えた場合
仮想通貨を無償で受け取った場合、贈与にあたる場合は年間110万円の控除枠を超えた場合には確定申告が必要です。 この他にも、給与の年間収入が2,000万円を超える場合や、住宅ローン控除、医療費控除などを希望する場合にも確定申告をすることとなります。 また、法人として仮想通貨を保有している場合は、年度末ごとに損益を計上する必要があるため注意しましょう。仮想通貨による所得の勘定科目
仮想通貨の所得を確定申告する場合は「雑所得」として計上します。雑所得の出し方は、利益確定時の仮想通貨の価格から購入時の仮想通貨の価格を引いた差額となります。仮想通貨の税率
通常、所得税の税率は1,000円 から 1,949,000円までは5%、1,950,000円から3,299,000円までは10%(控除額97,500円)、3,300,000円から6,949,000円までは20%(控除額427,500円)と所得額に応じて上がっていき、最大で4,000万円を超える所得には45%(控除額4,796,000円)まで課税されます。 しかし、仮想通貨の所得は他の所得との合算額に対する税率が適用されます。 例えば、仮想通貨の所得50万円のみが年間所得である場合の税率は5%となりますが、仮想通貨以外の所得が4,000万円を超える場合、仮想通貨の所得も45%で計算することとなるため注意が必要です。仮想通貨の所得計算の方法
仮想通貨の所得を計算する方法としては ・総平均法 ・移動平均法 の2つに大きく分けられます。 総平均法は、1年間の平均レートをベースに、取得した仮想通貨と売却金額それぞれの合計の差額を計上します。 移動平均法では、購入の都度差額を計上する方法です。 一般的には総平均法の方が計算は容易となりますが、どちらがよいかは使用するソフトや管理方法によっても異なるでしょう。 仮想通貨取引所や国税庁のホームページなどを確認し、履歴やレポートが入手できる場合はダウンロードするなどして、手元で資料として大切に保存するようにしましょう。仮想通貨の収入を申告しなかった場合どうなる?
仮想通貨の収入について、申告が必要な額の所得を得たにもかかわらず確定申告をしなかった場合にどうなるのかについて解説します。仮想通貨の所得隠しはばれやすい
税務署では、ほとんど全ての仮想通貨取引情報を調べることが可能です。そのため、どんな小さな取引でも隠すことはできないと考えた方がよいでしょう。「このくらいの利益ならばれないだろう」と考えていても、税務調査で指摘される可能性は十分にあります。 仮想通貨による所得に加え、申告が必要であるにもかかわらず確定申告をしていない無申告状態のケースについても、税務署はよく把握しています。税務調査は事前にある程度ウラが取れている場合に申請されるケースが多いため、所得隠しや無申告はばれやすいでしょう。仮想通貨の収入を申告しないとどうなる?
仮想通貨で申告が必要な額の利益を得たにもかかわらず申告をしていない場合、税務調査で発覚すれば無申告加算税や重加算税などのペナルティを受けることとなってしまいます。税務調査では直近の年度だけでなく、3~5年(悪質なケースでは7年)も遡って指摘され(国税通則法第70条1項)、重いペナルティの対象となるケースも少なくありません。仮想通貨の税務調査が不安な場合は税理士へ相談を
国税庁では、仮想通貨取引のチェックを強化しており、税務調査も積極的に行っていることをホームページでも公開しています。 「管理方法が間違っていないか気になる」「税務調査で指摘された場合ペナルティがいくらになるのかよくわからない」という場合は、仮想通貨の税務調査に明るい税理士などへ相談してみるようにしましょう。 税理士法人松本では、仮想通貨による所得の申告サポートや、税務調査の際の対応などの取扱い実績を多数誇っています。 元国税OB含む税務調査に特化した税理士が多数在籍しており、初回相談も無料で対応しています。 お問い合わせはフリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。まとめ
仮想通貨は保有しているだけでは申告の必要はないものの、利益が確定したり、他の仮想通貨と交換したりして利益が出た場合には課税対象となるため注意が必要です。 仮想通貨の所得について確定申告が必要かどうか、申告しなかった場合の追徴課税、きちんとしているつもりでも税務調査による指摘に不安がある場合には、税理士などの専門家からアドバイスをもらうことも検討してみましょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
印紙税にも税務調査がある?調査の種類や気をつけるべき点は?
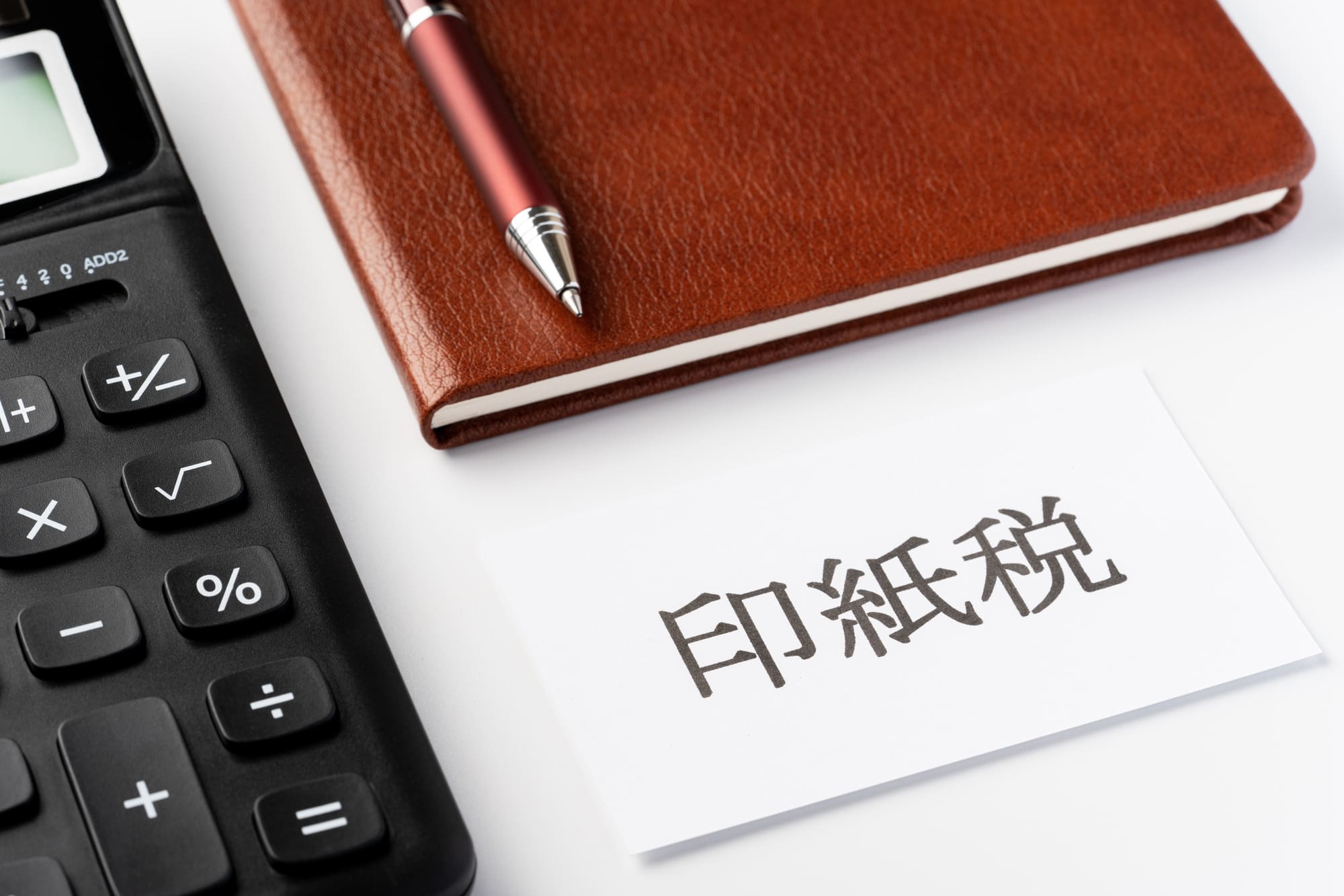
税務調査で調べられる税金は法人税や所得税、消費税など様々ですが、印紙税についても調査の対象となります。 印紙税の税務調査とはどのようなものなのか、どのような点を調べられるのかなどについて事前に知っておくことで、急な税務調査にも落ち着いて対応することができるでしょう。 この記事では、印紙税の税務調査の概要や調査の流れ、注意するべきポイントなどについて解説しています。 収入印紙を貼るべき書類がないか、貼り忘れた場合のペナルティなどについて知りたい際の参考にしてください。
印紙税の税務調査とは
はじめに印紙税の税務調査とはどのようなものなのか、その概要について解説します。契約書などに収入印紙の貼り忘れがないかをチェックされる
印紙税の税務調査とは、契約書や領収書などに収入印紙の貼付漏れがないかについて実施される調査のことです。 税務調査は納税者が税金を適正に申告、納税できているか、間違った処理をしている場合は正しく指導を行う目的で行われます。 印紙税についても同様に、印紙税が必要な場面で適正に扱われているかを調査されることとなります。印紙税の税務調査の種類
印紙税の税務調査は、以下の種類に大きく分けることができます。・同時調査
印紙税の他に、法人税や消費税など他の税金と同時に税務調査を行う方法です。印紙税の税務調査は、同時調査の形で行われるのが一般的です。・単独調査
印紙税の税務調査のみが単独で行われることを単独調査といいます。印紙税の単独調査は、一定以上の規模で事業を営んでいる事業者に対して行われることが多いものです。 事業内容や取引数、売上の規模などから、相当量の課税文書を発行していると思われる場合に、貼付漏れがないかを確認する単独調査が行われることがあります。 いずれの税務調査も確認するポイントは同じで、納税漏れが発覚すればペナルティの対象となる可能性があるため注意が必要です。印紙税の税務調査の流れ
印紙税の税務調査の大まかな流れについて解説します。同時調査の場合
同時調査で印紙税の調査が行われる場合は、通常の税務調査の流れの中で確認されることとなります。 法人税や所得税の税務調査を行いつつ、事業の概要や日常業務、収入印紙を購入している場合は使い道などについてヒアリングがあり、保存している書類の提示を求められる中に、収入印紙を貼るべき契約書や領収書などが含まれる流れとなります。単独調査の場合
印紙税の単独調査も、基本的には法人税や所得税の税務調査と似た流れを取ります。 一般的な任意調査では事前に税務調査を行う旨の連絡があり、指定された日に税務署または国税庁から調査官が調査に訪れ、1~2日程度を要して調査にあたる点も同様です。 印紙税の税務調査では、印紙税について重点的に調査されることとなるため、業務の流れや契約書、領収書などの作成方法、保管状況や毎月の書類作成数、収入印紙の管理方法などについて細かく質問を受ける可能性が高いでしょう。 普段の業務内容を確認し、実際の資料もチェックしながら、調査官は印紙の貼付が必要な課税文書がどの程度あるか、課税文書に対して収入印紙の購入額のバランスなどをチェックしていくこととなります。印紙税の税務調査で納付漏れが発覚したらどうなる?
税務調査で印紙税の貼付漏れが指摘された場合、貼り忘れた分の印紙税に加え、過怠税と呼ばれるペナルティが上乗せされることとなります。 過怠税では、貼り忘れた印紙税の2倍分の印紙税が追徴されることとなります。 例えば、税務調査で収入印紙の貼り忘れが30万円だった場合、30万円に加えて60万円の過怠税がかかってしまいます。 30万円分の収入印紙の貼り忘れが見つかった場合、最終的に90万円が課税されてしまうこととなるのです。 印紙税の未納が発覚することで、企業の信頼やブランド力が低下してしまうデメリットもあります。 法人税や経費については細かく管理していても、収入印紙についてはチェックしておらず、税務調査で明るみに出るケースも少なくありません。 過怠税で多額の追徴課税を受けることも避けたいところですが、脱税によって損なわれた起業やブランドイメージを回復する方が大変なケースもあるため注意が必要です。印紙税で指摘されないために気をつけるポイント
税務調査で印紙税の漏れを指摘されないためのポイントについて解説します。印紙の貼付漏れがないか確認する
まずは、税務調査にあう前に過去の書類をチェックし、収入印紙の貼り忘れがないかを確認しましょう。 収入印紙が必要となる書類には ・5万円以上の領収書 ・約束手形、為替手形 ・不動産売買、代理店契約、業務委託など継続的取引(3ヵ月以上)の基本となる契約書 ・請負契約書 などが挙げられます。 収入印紙の貼り忘れに加え、適正な税額の印紙が貼られているかもチェックします。 例えば、領収書の場合は税抜き金額が5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円となり、対応する金額によって印紙税額が異なります。 請負契約書の印紙税は1万円以上100万円以下が200円、100万円超200万円以下が400円、200万円超300万円以下が1,000円となっており、対応する契約金額によって印紙税が異なります。契約金額の記載がない契約書は非課税です。 継続的取引の基本となる契約書に貼付する収入印紙は一律4,000円となります。 上記で挙げた以外にも、契約金額について記載のある念書や覚書などは課税文書とみなされ、収入印紙が必要となる場合があります。また、証明書として保有するためにした契約書のコピーなども収入印紙が必要です。デザイン変更後の印紙の取扱いについて
税務調査で指摘されやすいケースの1つに、収入印紙のデザインも挙げられます。収入印紙のデザインは平成30年7月に新しいデザインとなったため、平成30年7月より以前の課税文書に新しいデザインの収入印紙を貼っている場合、税務調査の直前に貼った疑いを持たれる原因となるため注意しましょう。貼り忘れが判明したら自主申告する
印紙税の貼付漏れを見つけた場合、自主申告すれば過怠税は1.1倍となります。自主申告以外では過怠税が合計で3倍となってしまうため、早期に自主申告をするのも1つの方法です。なお、自主申告で印紙税を納めた場合、納付後に書類へ収入印紙を貼ると印紙税の二重計上となってしまうため注意しましょう。電子書類へ切り替える
収入印紙の貼付が必要な課税文書は紙の文書に限られるため、電子契約書などのデータによる書類であれば、印紙税を納付する必要はありません。印紙税を見直すタイミングで、電子契約書へ切り替えることも検討するとよいでしょう。印紙税の税務調査が不安な場合は専門家へ相談しよう
「どの書類に収入印紙を貼ればよいのかわからない」「税務調査で印紙税を指摘されないか不安」という場合は、税務調査の対応実績が豊富な専門家へ相談してみましょう。 税理士法人松本では、税務調査で指摘されやすいポイントを熟知したプロの税理士が多数在籍しています。印紙税に関する相談はもちろん、税務調査でチェックされやすいポイントについても丁寧に対応いたしますので、一度お気軽にお問い合わせください。まとめ
印紙税の税務調査は、法人税や所得税の税務調査のついでに行われる同時調査と印紙税をメインに調査される単独調査に大きく分けられます。印紙税の税務調査では、貼付するべき収入印紙が適正に扱われているかをチェックされることとなります。印紙税の貼付漏れが発覚した場合、多額の過怠税が課せられることとなり、企業の信用が低下するリスクもあるため、専門家へ相談しながらしっかりと管理することが大切です。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
使途不明金とは?税務調査で注意するべきポイントをわかりやすく解説

計上した経費の中に「使途不明金」が含まれていると税務調査で指摘された場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。使途不明金とはどのようなものなのか、税務調査で注意するべきポイントなどについても気になるところです。 この記事では、法人の経理担当者様や法人・個人を含む経営者様に向け、使途不明金の概要や税務調査で指摘された場合の流れなどについてわかりやすく解説しています。 税務調査での注意点や対策などについても紹介していますので、過去の申告内容や税務調査に関する疑問を解消する際の参考にしてください。
使途不明金とは
まずは、使途不明金とはどのようなものなのか、その概要について解説します。支出の目的が不明で損金計上できない支出のこと
使途不明金とは、使い道のわからないお金のことで、支出の目的が不明で損金計上できない支出のことをさします。 経費を計上する際、「接待交際費」や「旅費交通費」など、様々な勘定科目を使うのが一般的です。 法人税や所得税を申告する際に、該当する勘定科目を使って経費としたにもかかわらず、本当に業務上必要な経費か不透明である場合、使途不明金とみなされる可能性があるのです。使途不明金は税務調査で指摘されやすい
使途不明金は、税務調査を受けた際に指摘されやすいポイントの1つでもあります。 例えば、消耗品費として計上している支出があったとしても、対応する領収書がない場合、本当に消耗品費として使われたことが証明できなくなってしまいます。 仮に領収書があったとしても、業務上必要な消耗品なのか、プライベートな買い物ではないのかなどが不明な場合は、使途不明金ではないかと指摘を受ける可能性があります。税務調査で使途不明金とみなされた場合はどうなる?
税務調査で使途不明金の指摘を受けた場合にどうなるのかについて解説します。損金算入できず、修正申告となる
税務調査で過去に申告した支出の内容について使途不明金であるとの指摘を受けた場合、該当する支出については損金計上をすることができなくなってしまいます(損金不算入)。 経費として認められる支出が減るため、過少申告であるとみなされ、修正申告をして不足分の税金を納付する必要があります。ペナルティの対象となるケースも
使途不明金とみなされた場合、過少申告分を修正申告するだけで済まないケースもあります。 税務調査で意図的な経費の水増しや書類の偽造、証拠隠滅などを疑われた場合、重加算税などのペナルティが課される可能性があるのです。使途不明金と使途秘匿金の違い
使途不明金のほかに「使途秘匿金」と呼ばれるものもあります。税務調査で使途秘匿金とみなされた場合も、損金不算入となります。 使途秘匿金とは、使い道を意図的に隠して損金算入したとみなされる支出のことです。 使途不明金が使い道の不明な支出であるのに対し、意図的に使い道を隠す使途秘匿金の方が悪質だとみなされます。 税務調査で使途秘匿金との指摘を受けた場合、使途秘匿金の40%を法人税として上乗せして納付しなければならなくなります。 例えば、申告内容のうち100万円が使途秘匿金とみなされた場合、損金不算入で過少申告した分との差額に加え、40万円が上乗せされることとなります。 延滞税や重加算税が課される可能性もあるため、使途秘匿金とみなされれば多額の追徴課税が発生する可能性が高まるため注意が必要です。 使途不明金、使途秘匿金が疑われる要件としては ・計上するべき勘定科目で計上されていない ・書類や資料の破棄、隠匿、改ざんがある のいずれかに該当する場合であるとされています。 法人が支払った金銭のうち、支払先の名称や所在地、支払いの名目などが記載されていない場合に使途秘匿金とみなされることが租税特別措置法で定められています(租税特別措置法第62条2項)。使途不明金について税務調査で注意するポイント
使途不明金について税務調査で注意するべきポイントについて解説します。支払いの目的や詳細をメモに残す
税務調査で使途不明金を疑われないためには、支払いの目的や詳細をメモや印刷などで詳細に残しておくことが大切です。 例えば、取引先への配布を目的に購入したギフト券を接待交際費として計上した場合、領収書を保管していたとしても使途不明金を疑われる場合があります。 配布先に「関係者各位」「取引先」といった曖昧な記載しかしていない場合、誰に何枚配布したのか、本当に配布したのかといった疑問が残ってしまいます。 税務調査がやって来る旨の連絡を受けてから慌てて配布先のリストを作成しても、計上した日付から長期間経過した後に作られたことがわかる場合、リストの信ぴょう性は低いと判断されがちです。 外注費として個人へ報酬を支払った場合も「外注費として○○様へ5万円」の情報だけでは、何の用途で支払われたお金かが不明となってしまいます。 税務調査の際に使い道が不明だと思われないように詳細を資料として残し、用途を質問された際にも、詳細について答えられるようにしておくことが大切です。接待交際費の扱いについて
接待交際費の計上について、法人と個人では若干ルールが異なります。 法人で接待交際費を計上する場合、経費の無駄遣いを防ぐ目的で一定の限度額を設けて、限度を超えた交際費については損金として計上しないこととされています。 資本金が1億円以下の中小企業の場合、交際費は800万円が控除限度額とされており、接待交際費の50%と比較して高い方を損金算入できることとなっています。 個人事業主の場合、接待交際費の計上について法人のようなルールはありませんが、収入と比較して接待交際費が多額にのぼる場合には、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。 税務調査で接待交際費とみなされる条件としては、支払先の名称、所在地、使途が記帳されている必要があります。 接待交際費が飲食代の場合には、接待した相手の氏名、屋号や関係性、参加人数などの記載も必要となるため注意が必要です。税務調査で使途不明金とみなされないか不安な場合は税理士へ相談を
「現在の記帳では税務調査で使途不明金とみなされるのではないか」と不安な場合は、税務調査対応の取扱い実績が豊富な税理士へ相談してみることをおすすめします。 早めに相談して対応してもらうことで適正な申告ができるだけでなく、税務調査が来た場合も安心して対応することができます。 不慣れなケースに悩むことなく、安心して事業に集中することができるようになるでしょう。 税理士法人松本では、元国税OBを含む税務調査の内情を熟知した税理士が、ケースごとに丁寧にお話を伺い、最適なご提案をしています。 お問い合わせはフリーダイヤルまたはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。まとめ
使途不明金とは使い道が不明な支出のことをさし、経費として計上したものが税務調査で使途不明金とみなされると、損金算入できずに修正申告しなければならなくなります。 使途秘匿金の疑いが出た場合は、更に使途秘匿金の40%が法人税に上乗せされ、重加算税などのペナルティの対象になる可能性もあります。 使途不明金や使途秘匿金を疑われないためには、接待費や外注費の支払先詳細を帳簿へ残し、飲食代については参加人数や参加者との関係性、氏名や名称なども詳細に残しておく必要があります。 不安な場合は税理士などの専門家へ相談しながら、税務調査対策を進めていきましょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務調査でばれるカラ出張とは?指摘されない対策を解説!

税務調査を受けた際、旅費交通費を「カラ出張」として指摘されるケースがあります。カラ出張を疑われてしまうのは、どんな理由からなのでしょうか。 この記事では、税務調査でカラ出張ではないかと指摘される理由や対策についてわかりやすく解説しています。 旅費規程を作る際のポイントについても紹介していますので、旅費交通費の申告内容について不安がある際の参考としてお役立てください。
税務調査でカラ出張を疑われる理由
税務調査でカラ出張を疑われる理由としては、以下のような点が挙げられます。プライベートとの線引きが難しい旅費交通費
旅費交通費は原則非課税で、交通費の中には電車利用などで領収書が取得できない場合も少なくありません。 規定に基づいた適正な交通費であれば、実費精算しなくてもよいこととなっているため、経費の水増しを目的に不正な旅費交通費の計上をしているケースが起こりやすくなっています。 私的な旅行や移動手段として使われた交通費と業務上の理由で使う交通費を厳密に分けるのは難しいケースも多く、プライベートとの線引きが難しい場合もあります。 そのため、税務調査において旅費交通費の内訳は指摘を受けやすい項目の1つともなっています。そもそもカラ出張とは?
税務調査で指摘される「カラ出張」とは、実際には行っていない出張にかかった交通費や宿泊費などを旅費交通費として計上することをさします。 カラ出張で悪用されやすい方法としては ・実際には行かない出張申請を出し、旅費や日当を経費計上する ・新幹線のチケットを予約して交通費を計上し、後日払い戻す ・予約した宿泊先をキャンセルし、宿泊費の安いホテルを利用して差額を着服する ・出張先で実際には利用していない地下鉄やバスの料金を計上する ・プライベートの旅費や宿泊費を出張費として計上する などが挙げられます。旅費交通費の定義
旅費交通費とは、業務上必要とされる場所へ出張する際にかかる交通費や宿泊費、経費などをさします。 旅費交通費に該当する費用としては ・電車、バス、飛行機、フェリー、タクシー代などの交通費 ・社用車で出張した際の駐車場代、ガソリン代、高速代 ・レンタカーを使用した場合の利用料 ・宿泊費 ・海外出張時のビザ、パスポート申請費用 などが挙げられます。 旅費交通費について規定を作成していないと、高級ホテルやタクシーの頻繁な利用などの可能性も出てしまいかねません。 特に、出張する従業員へ旅費の管理を任せている場合にはカラ出張の不正が起きやすく、税務調査で指摘されてはじめて発覚するケースも少なくないのです。カラ出張を指摘されないために取るべき対策
税務調査でカラ出張を指摘されないためには、以下のような対策が重要となります。出張旅費規程を作る
旅費交通費の使い方について社内規定を設けてルール化することで、高額な旅費交通費の申請、計上を防ぎ、税務調査で不透明な経費計上を疑われるリスクを避けやすくなります。 旅費規程の内容については特に法律で定められていないため、適正な範囲で会社ごとに作成することが可能です。社内で作った旅費規程は、労働基準法によって就業規則として扱われます。 出張旅費規程を作成する際には ・規定を作成する ・社内全員へ周知する ・株主総会で決議決定する といった流れで行います。出張旅費規程で定める主な内容
旅費規程で定める内容としては、以下が挙げられます。・出張の定義
どこまでの移動を出張と定義するかを定めます。一般的には、宿泊をともなう場合、片道100kmを超えた場所へ移動する場合に出張と定義されます。・適用範囲
出張にともなう旅費交通費の支給を社員に限定するか、契約社員やパート、アルバイトも含まれるのかなどを定めます。・出張手当と宿泊費
出張時に支給される手当と宿泊費を定めます。 産労総合研究所が2019年6月に行った調査によると、宿泊出張時手当の平均額は部長職が2,900円、一般社員が2,355円となっていました。 宿泊費については部長職クラスで9,835円、一般社員で8,605円となっています。 参照元: 産労総合研究所「2019年度 国内・海外出張旅費に関する調査」・グリーン車、座席等級など
新幹線を予約する際にグリーン車料金を認めるか、飛行機の座席にビジネスクラス使用を認めるか、フェリー乗船時の座席クラスなどについて定めます。 なお、産労総合研究所のデータでは、新幹線のグリーン車使用は「都度判断する」を含め、部長職クラスでの使用を認めているケースが18.1%となっていました。・出張先での経費をどこまで認めるか
出張先でかかる交通費、宿泊費以外の経費について定めます。社員の飲食代などを福利厚生費として認めるかどうかなどが挙げられます。 この他にも、出張の申請方法や出張費の仮払い手続き、費用の明細提出方法などについて定めます。出張旅費規程を作成する際のポイント
出張旅費規程を作成する際のポイントについて解説します。適正な金額を定める
宿泊費や出張手当に関する規定を作る際は、適正な範囲で定めるようにしましょう。 相場よりも大きく相違した金額や、多額の出張費を設定すると、税務調査で経費の水増しを疑われる可能性が高まります。 適用には一定のルールを決めて社員全員に周知し、申請方法や精算方法を継続して守ってもらうようにします。定期的に見直しを行う
出張手当や宿泊費、その他諸経費などの平均額については、地域によって差があったり、物価の変化によって異なってきたりするケースもあります。 定期的に見直しを実施し、必要に応じて都度適正額を規定し直すようにしましょう。領収書や明細などの資料は必ず保存する
タクシー代や新幹線のチケット代、宿泊費や現地での経費など、領収書や控えが取得できるものについては必ず提出してもらい、ファイリングして管理するようにします。 出張先にある取引先の会社概要や商談時に入手した名刺、出張する必要があることを証明する企画書なども資料として保存しておくとよいでしょう。出張旅費規程の作成で迷った場合は税理士へ依頼しよう
出張旅費規程の作成方法で迷った場合や、税務調査で指摘されない管理方法について知りたい場合は、税理士などのプロへ依頼するのも1つの方法です。 税理士法人松本では、国税OBを含む税務調査に特化した税理士が多数在籍しています。税務調査で問題となるポイントやカラ出張を疑われないための改善方法などについて、プロのノウハウを活かしたアドバイスが可能です。 経営に関するサポートやコンサルティング業務などにも柔軟に対応していますので、旅費規程の作成や税務調査対応でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。まとめ
税務調査では旅費交通費についてチェックされることが多く、カラ出張を疑われると経費として認められず、過少申告や偽装、脱税などを疑われる原因になる可能性があります。 旅費交通費は実費精算でなくてもよく、プライベートな利用や高額な宿泊費、チケットなどを計上できるケースもあるため、出張旅費規程を定めて税務調査で適正に計上していることを説明できるようにしておくことが大切となります。 出張旅費規程の適正な作り方に少しでも不安がある場合や、税務調査で指摘されないための改善点などについて知りたい場合は、1人で悩まずに実績豊富な税理士などの専門家へ依頼する方法も検討してみるとよいでしょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Suicaのチャージ代は経費にできる?税務調査で指摘されやすい理由は!

近年活用頻度が高まっているSuicaや電子マネーは、チャージ代をいつ経費計上できるのかで迷いやすいものです。 Suicaへのチャージ代計上を税務調査で指摘されることはあるのか、あるとすればその理由や、チャージを経費にする際のポイントなども知っておきたいところです。 この記事では、Suicaや電子マネーへのチャージが税務調査で指摘されるポイントや、正しい経費計上の方法などについてわかりやすく紹介していきます。
Suicaへのチャージは税務調査で指摘される?
Suicaへのチャージは、税務調査でどのように指摘されるのかについて解説します。Suicaへチャージしただけでは経費とみなされない
Suicaに限らず、電子マネー全般へチャージしただけでは、原則として経費とは認められません。 Suicaへのチャージは、現金を電子マネーに代えただけに過ぎないため「現金を自分の銀行口座へ預け入れた」「銀行から引き出した現金を財布へしまった」といった行為と同じであるといえるのです。 Suicaを早期に導入した場合「チャージした時に経費にしてもよい」と専門家からアドバイスされていたケースがあるかもしれません。 Suicaへのチャージが電車賃とイコールになっていると認識している人も少なくないでしょう。Suicaへのチャージが経費とみなされるタイミングは?
経費とみなされるのは、チャージした金額を使って交通機関を利用した時点となります。 毎回決まった時期に定額をチャージし、すべてを交通費として使用している履歴などがわかれば、チャージした時点で経費計上しても最終的に認めてもらえる可能性はあります。 しかし、もしもチャージした金額を経費以外の用途に使用した疑いがある場合、税務調査で指摘を受けてペナルティの対象となる可能性が高まってしまいます。税務調査でSuicaなどのチャージを指摘されやすい理由
税務調査でSuicaへのチャージについて指摘されやすい理由として、以下のような点も挙げられます。私的な目的に使用されやすい
Suicaや電子マネーへチャージした場合、チャージした金額のすべてが交通費として使用されるとは限らない仕様となっています。 Suicaへチャージした現金は、Suicaでの決済に対応している店舗でのショッピングに使うことが可能です。 そのため、Suicaへのチャージを経費として計上しながら、実際にはプライベートな目的で使っている可能性がないかを税務調査ではチェックされることとなるのです。 税務調査でSuicaのチャージをプライベートな目的で使用したとみなされた場合、経費の計上が認められないため、その分の法人所得の修正が必要となります。 また、会社役員への給与として扱われる場合には、源泉所得税の徴収漏れも指摘されることとなるでしょう。二重計上されている場合がある
Suicaのチャージ時点で経費として計上し、チャージを使用した際にも経費計上する「二重計上」が行われやすい点も、税務調査で指摘を受ける理由の1つとなっています。 チャージした時点で経費計上したことを忘れて、うっかりコンビニなどでSuicaを使用し、購入した際のレシートを経費のレシートに含めてしまい、二重計上となってしまうケースは見落としやすいものです。 意図的に二重計上したわけではなかったとしても、税務調査で疑いを持たれるような点が随所に見られれば、経費の水増しや私的な着服などが疑われる可能性も出て来てしまいます。明細がわからないケースも多い
Suicaへチャージした際の履歴は残っていても、実際にいつどの時点でいくら使用したかがわかる明細を保存していないケースもあります。 Suicaの利用履歴はチャージ専用機で印字することができますが、最大で100件までしか遡ることができないため注意が必要です。 うっかり印字を忘れると明細が提示できなくなってしまい、税務調査で指摘されるケースもあります。 うっかりミスによる二重計上や利用履歴の明細提示ができない、といった事態が重なってしまうと、税務調査で横領や脱税、所得隠しなどを疑われる原因になりやすいのです。Suicaや電子マネーへのチャージを経費にする際のポイント
Suicaのチャージ利用をいい加減に管理していると、税務調査で指摘されやすいため注意が必要ですが、Suicaの利用は便利なため、業務上では活用したいところです。 Suicaや電子マネーへのチャージを活用して経費にする際に気をつけるべきポイントについて解説します。仕事専用のSuicaを持つ
可能であれば、仕事専用のSuicaを作ってプライベートと完全に分けてしまうとよいでしょう。 仕事以外の目的で使用していないと説明できる状態にすることで、税務調査で疑われるリスクを減らすことができるうえ、会計管理もわかりやすくなるメリットがあります。 私的な買い物をしている疑いを持たれないよう、仕事専用のSuicaはシンプルに交通費の決済専用として使用した方がよいでしょう。利用時に経費計上し、二重計上されないようにする
Suicaや電子マネーへチャージした時点ではなく、交通機関を利用した時点で経費計上するようにしましょう。 間違ってチャージ時点で経費にしてしまい、改札利用時にも経費計上してしまわないよう、次に紹介する明細や履歴の保存と併せて管理することをおすすめします。 チャージ時点で経費計上している場合も、年度末までに使い切っているのであれば問題はありません。 もし年度末にチャージ残額がある場合は、その分を「貯蔵品」の勘定科目を使用するなどして、損金算入しないように管理します。明細や履歴を保存しておく
Suicaの利用履歴がわかる明細はこまめに印字したり、アプリ使用で履歴を保存したりできるようにしておきましょう。 現金払いや回数券使用など、他の決済方法による交通費がある場合は、エクセルなどで表管理しておくと見やすく便利です。 Suicaを使った交通費の処理や仕訳についてマニュアルを作成し、二重計上や私的流用などが起きないよう管理していると説明できるような体制を作っておくと、税務調査の際に説明がしやすくなるでしょう。Suicaのチャージについて不安な場合は実績豊かな税理士へ相談しよう
Suicaのチャージといった決済方法について詳しい知識がないと、専門家でも「チャージした時点で経費にしてもよい」と間違った指導をしてしまう可能性があります。 Suicaや電子マネーのチャージに関する記帳や仕訳については、近年の決済手段に対する税務調査対応などの実情に明るい税理士へ相談することが大切です。 税理士法人松本では、税務調査に関するご相談はもちろん、経理業務のアウトソーシングや税理士のセカンドオピニオンを聞きたい、といったご相談にも対応しています。 初回の電話相談は無料、フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームより相談予約を受け付けていますので、一度お気軽にご連絡ください。まとめ
Suicaや電子マネーのチャージは、チャージした時点では経費とはみなされないのが一般的です。 そのため、チャージした金額の明細のみを保管して経費計上している場合、税務調査で指摘を受けやすいため注意が必要となります。 Suicaのチャージは交通費以外に、コンビニなどで買い物する際にも利用できるため、私的な流用や二重計上が疑われやすく、過少申告としてペナルティの対象となってしまいます。 Suicaのチャージを税務調査で指摘されないためには、仕事専用のSuicaを発行し、交通機関などで利用した時点で経費計上し、利用明細は保管してしっかりと管理することが大切です。 現在の申告内容や仕訳に不安がある場合は税理士へ相談しながら、適正な申告になるように注意しましょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務調査から横領がばれる理由や事例を紹介

税務調査で横領がばれるのには、どのような理由があるのでしょうか。 多額の横領事件がメディアを賑わせるのを見かけたことがある方も多いでしょう。 この記事では、横領は税務調査でなぜばれるのか、ばれる理由や横領が発覚しやすい事例などについて紹介しています。 税務調査で横領を疑われないための対策についても解説していますので、申告内容についての不安を解消する際の参考としてお役立てください。
税務調査で横領がばれる理由
税務調査で横領がばれる理由について解説します。素人ではわからない工作もプロにはばれてしまう
横領の事実は、しばらくの内は隠し通せたとしても、どこかのタイミングで必ずばれることとなります。 人事異動や組織再編などで風通しが変わってばれるケースや、内部通告などによって問題としてフォーカスされ、社内調査によって発覚するケースなどもありますが、税務調査はもっとも横領がばれやすいタイミングの1つでしょう。 税務調査で横領がばれやすい理由の1つとして、税務調査にあたる調査官は長年に渡り多くの税務調査に携わっているプロである点が挙げられます。 税務調査は、納税者を適正な申告、納税へ導くことを目的として行われています。 同じ業種や規模の会社におけるお金の流れや取引の履歴、財務状況についても、間違いや不正がないかを徹底的に調べられるデータベースを持っているため、申告漏れが起きやすいケースや所得隠し、脱税や横領を隠すための手口についても熟知しているのです。 この他、第三者からのタレコミなどによって、あらかじめ情報を掴んだ上で税務調査にやって来る場合もあるでしょう。架空発注などで共謀していた取引先が税務調査にあい、そこからばれるパターンなどもあります。こんな資料は横領がばれやすい
税務調査で税務署がチェックする主な資料としては ・申告書類:法人税、所得税、消費税の申告書類、源泉徴収票など ・帳簿書類:総勘定元帳、仕訳帳、売掛帳、現金出納帳など ・原始資料:領収書、請求書、預金通帳、契約書など などが挙げられます。 この他にも、タイムカードや在庫票、会社概要や組織図などの提示を求められる場合もあります。 横領がばれる際には「誰が横領したか」「どこから横領したか」の2点に関する証拠を集めていくこととなります。 領収書や発注書を調べただけでは一見わからないように工作していても、実際の入出庫票や棚卸に関する過去の履歴との比較、取引先を訪問した回数や日付、担当者の行動履歴など、様々な角度で複数の資料をチェックすることで横領の疑いが濃厚になっていきます。 上記で挙げた税務調査でチェックされやすい資料については、すべて横領がばれるきっかけになり得ると考えた方がよいでしょう。税務調査でばれる横領の事例
税務調査の結果でばれてしまう横領の具体的な事例を以下で見ていきましょう。事例1:集金の着服がばれたケース
A社の担当者がB社へ集金した際に領収書を発行し、その控えを会社に残さず代金を着服したというケースでは、取引先の現金出納帳や領収書などをチェックしたことで横領が発覚しました。 A社にはB社から代金を回収したことを証明する資料が残っていなくても、B社へ税務調査を行った際に取引履歴などを資料化し、後日A社の税務調査に活用される場合があります。事例2:外注費を水増ししたケース
友人などと共謀し、自社から外注先へ費用を支払うと見せかけて友人宛てに外注費を支払い、その費用を山分けするなどして横領したケースでは、外注先との間で交わした架空の請求書や領収書をチェックし、外注先の申告状況などを調べた結果、外注の事実がなかったことが判明しました。 外注先として記載されていた氏名や所在地から申告状況を調べた結果会社員であるとわかり、依頼内容などについて質問すると答えられなかったなど、ポイントを押さえて追及していくと横領の疑いが濃厚となっていきます。横領の手口は業種や部署によっても異なる
上記で挙げた横領がばれる事例はほんの1例で、実際の手口は業種や部署、事業規模によって様々となります。 建設業など外注が多い企業では水増しもしやすく、仕入を伴わないサービス業であれば集金の着服などがしやすくなるでしょう。 個人事業主の場合、実際は外注していないのに架空の外注先を作って経費を水増しする、といった手口も可能です。 税務調査では、こうした様々な手口に対してポイントを押さえて調査を行い、独自のルートを活用して得た情報から分析することも可能なため、横領を隠そうとするほどばれやすくなります。 社内で横領事件が発覚した場合、当事者である従業員が処罰されるのはもちろんのこと、税務上は会社の不正と思われてしまったり、代表者や役員も処罰の対象となり、取引先にも迷惑がかかったりするリスクもあるため注意が必要です。税務調査で横領を疑われないためには?
税務調査で横領を疑われないための対処法について解説します。しっかりと説明できるように準備しておく
実際には横領していなくても、それを証明できる書類や資料がなく、申告漏れや計上ミスなどが重なってしまった場合、横領を疑われてしまう可能性があります。 故意でなかったとしても、税務調査で申告漏れが発覚したり、領収書が見当たらなかったりすれば、なんとなく焦ってしまって毅然と説明できず、ますます怪しまれてしまうケースも少なくありません。 日頃からダブルチェックや書類の保管を心がけるのはもちろん、いつ税務調査が来てもいいように、チェックされやすい書類や資料はファイリングして管理しておくことが大切です。 イレギュラーな取引などがあった場合は、備考やメモなどに経緯を書き留めておき、メールの履歴や添付資料などはパソコン内に保管しておくようにしましょう。適正な申告を心がける
申告漏れや無申告期間などがあると、意図的な脱税や横領などを疑われやすくなってしまいます。 現在進行形の取引はもちろん、既に完了している申告内容についても修正の必要がないか、定期的にチェックするようにしましょう。 社内での会計管理にかんするマニュアルや監査システムなどを策定して運用している事実があれば、悪質性を疑われるリスクを下げやすくなるでしょう。税務調査への対応に不安があるなら専門家へ相談を
税務調査は毎年来るものではないため、なかなかスムーズに対応するのは難しいものです。 曖昧な返事をしてしまったり、横領を疑われるような言動をしてしまったりしないか不安に感じるケースも多いでしょう。 正しいと思って申告していても、思わぬミスが見つかる可能性も少なくありません。 税務調査への対応に自信がなく、過去の申告内容も適正かどうかわからない場合は、一度税理士などの専門家へ相談してみることをおすすめします。 税理士法人松本では、個別の状況を丁寧に伺い、税務調査対応の実績豊富な税理士が誠実に対応いたします。 横領の疑いや無申告、税務調査後の追徴課税などについても対応していますので、まずは一度お問い合わせください。まとめ
税務調査では、税務署の独自ルートや調査網などを活用し、ポイントを押さえた調査が行われるため、横領はもちろん、脱税や所得隠しなどがばれやすいタイミングとなっています。 横領行為をしていなくても、証拠がなく説明もできないでいると、疑いを強められるリスクもあるため、税理士などの専門家へ相談して対応することが大切となります。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務調査で逮捕される可能性は?流れやペナルティについても解説!

税務調査で逮捕される可能性があるのか、不安や疑問に思う方も多いのではないでしょうか。修正申告やペナルティの対象になることに加え、逮捕されるケースはあるのか、その場合の流れや対処法なども知っておきたいところです。 この記事では、税務調査で逮捕される可能性や脱税による刑事手続きの流れに加え、脱税を疑われないためのポイントなどについてわかりやすく解説しています。
税務調査で逮捕される可能性はあるのか
まずは、税務調査で逮捕に至る可能性について解説します。税務調査で逮捕されるケースはある?
結論から言うと、税務調査で逮捕に至る可能性は決して多くはないものの、ゼロではありません。 管轄の税務署から調査官がやって来て行われる「任意調査」と呼ばれる税務調査においては、ほとんどの場合申告漏れなどが判明しても、逮捕にまで至るケースにはならないことが多いでしょう。とはいえ、調査中に悪質であると判断された場合には、任意調査から強制調査に切り替えられ、逮捕されてしまう可能性もあります。 なお、税務署ではなく国税局の査察部が行う調査は強制調査となり、既に裁判所から令状を取得して調査にやって来るため、逮捕される可能性はより高まることとなります。 ただし、強制調査の場合でも、逃亡の恐れがないとみなされれば、多額の不正や脱税とみなされた場合でも逮捕に至らない場合もあります。税務調査で脱税による逮捕を防ぐ対処法については、後ほど詳しく解説していきます。税務調査で逮捕の可能性がある犯罪の種類
税務調査によって逮捕される犯罪の種類としては、以下のようなものが挙げられます。 ・逋脱(ほだつ)犯:虚偽の過少申告や無申告による脱税 ・申告書の不提出逋脱犯:故意に申告書を提出しない ・不納付犯:預かった源泉所得税を故意に納付しない ・滞納処分免脱犯:滞納による差し押さえを回避する目的で財産隠しなどを行う ・間接脱税犯:密輸や密造による関税、酒税などの脱税 ・虚偽申告犯:申告書に虚偽がある ・単純無申告犯:正当な理由がなく申告をしていない ・検査拒否犯:税務調査の妨害や拒絶、改ざんした書類の提出などを行う このほかにも、納税者に申告や納税をさせないように妨害する「扇動犯」や、源泉徴収の義務があるにもかかわらず源泉所得税を徴収しない「不徴収犯」などの種類があります。税金に関わる犯罪によるペナルティ
上記で挙げた犯罪のうち、例えば逋脱犯の場合は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または懲役刑と罰金刑の両方が課せられます。 故意による申告書不提出逋脱犯では5年以下の懲役または500万円以下の罰金、または懲役刑と罰金刑の両方が課せられます。 虚偽申告犯や単純無申告犯、検査拒否犯では、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなります。 また、逮捕に至らない場合でも、税務調査で申告漏れや無申告などが発覚した場合は「過少申告加算税」「不納付加算税」「無申告加算税」「重加算税」といった追徴課税がペナルティとして課せられることとなります。脱税による刑事手続きの流れや事例
脱税で逮捕される際の刑事手続きの流れや、脱税で逮捕に至る事例などについて解説します。刑事手続きの流れ
脱税による刑事手続きの大まかな流れとしては、以下のようになります。 ・調査 ・告発 ・逮捕 ・起訴、裁判 税務署または国税局査察部による強制調査が実施され、脱税や不正行為が発覚すると、調査官や査察官は検察へ告発を行い、告発を受けた検察官が捜査を進め、脱税や不正の疑いが濃厚な場合に逮捕されます。 しかしながら、脱税は多額だが、容疑者に逃亡の恐れがない、かつ証拠隠滅などの可能性も低いケースでは、逮捕されず在宅で起訴が進められます。 逮捕された場合は、原則として逮捕から48時間以内に起訴か不起訴を決定しますが、判断がつかない場合は10~20日ほど拘留されることも考えられます。 起訴された場合は裁判へと進み、有罪となれば刑が確定となるのが一般的な流れです。脱税で逮捕に至る事例
脱税で逮捕に至る事例としては、以下が挙げられます。 ・売上の虚偽申告 ・虚偽の経費計上 ・不正な消費税の還付 ・無申告 このほかにも、税務調査の妨害や申告書の不提出など、逮捕となる可能性がある犯罪として挙げられた行為に該当する場合は、逮捕される可能性があるでしょう。 過去に脱税によって逮捕された事例としては、経費や損失の架空計上、売上の過少計上などで数千万円~数億円前後の脱税が発覚したケースなどが挙げられます。 冒頭でも解説の通り、一般的な任意調査で逮捕に至るケースはほとんどありませんが、国税局査察部による強制調査が実施された場合には、逮捕に至る割合は8割ほどにまで高まります。参考までに、令和4年度における国税局査察部による告発件数は103件、1件あたりの脱税額は約9,700万円、告発率は74.1%となっています。 参照元: 国税庁「令和4年度 査察の概要」税務調査で脱税の疑いをかけられないためには?
税務調査で脱税の疑いをかけられないためのポイントについて解説します。脱税を疑われないためのポイント
税務調査で申告漏れや計上ミスなどが発覚した場合、中には「申告しないといけないことを知らなかった」というケースもあるでしょう。しかし、税法についての知識がないからと言って、脱税してもよいということにはなりません。もしも意図的に脱税を行ったのではないかと疑われた場合には、証拠となる書類や資料などを提示して毅然とした態度で説明できるようにしておくことが大切です。 また、自分以外の従業員が脱税行為を犯し処罰された場合、法人の代表者や責任者となる個人事業主も処罰の対象となってしまいます。会計管理のマニュアル作成や定期的な業務チェックを行い、その証拠を残しておくことも重要となります。 資料や書類、メモなどは保存して見やすく月別、項目別にファイリングし、要望があればいつでも提示できるようにしておきましょう。税務調査で脱税を疑われないか不安な場合は税理士に相談しよう
税務調査で脱税を疑われないためには、適正な申告と納税を守ることに加え、疑われそうなポイントを押さえて対策をとっておくことが大切となります。既に申告済みの期間についても修正点がないか見直しを行い、必要に応じてマニュアルや内部規定なども作成します。 「申告内容が正しいか自信がない」「税法上問題があるかどうかの判断が難しい」という場合には、税務調査への対応実績が豊かな税理士へ一度相談してみましょう。 税理士法人松本では、国税OBを含む税務調査に特化した税理士が多数在籍しています。法律上問題のない節税対策や通常の税務相談、経理業務のアウトソーシングまで幅広く対応していますので、税務申告でお悩みの際はお気軽にご連絡ください。まとめ
税務署による任意調査で逮捕に至るケースは滅多にないものの、国税局査察部による強制調査では、全体の8割近くが脱税で告発されています。一般的な税務調査であったとしても、脱税の疑いが濃厚となった場合には強制調査に切り替えられ、証拠隠滅や逃亡の危険があるとみなされれば逮捕、拘留となる可能性もゼロではありません。 脱税を疑われないためには適正な申告、納税に加え、証拠となる資料や書類を提示して毅然と説明できることが大切です。不安な場合は税理士へ相談して、問題点があれば早めにクリアにしておきましょう。免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務調査の追徴課税の平均額は?個人の場合はいくらになる?
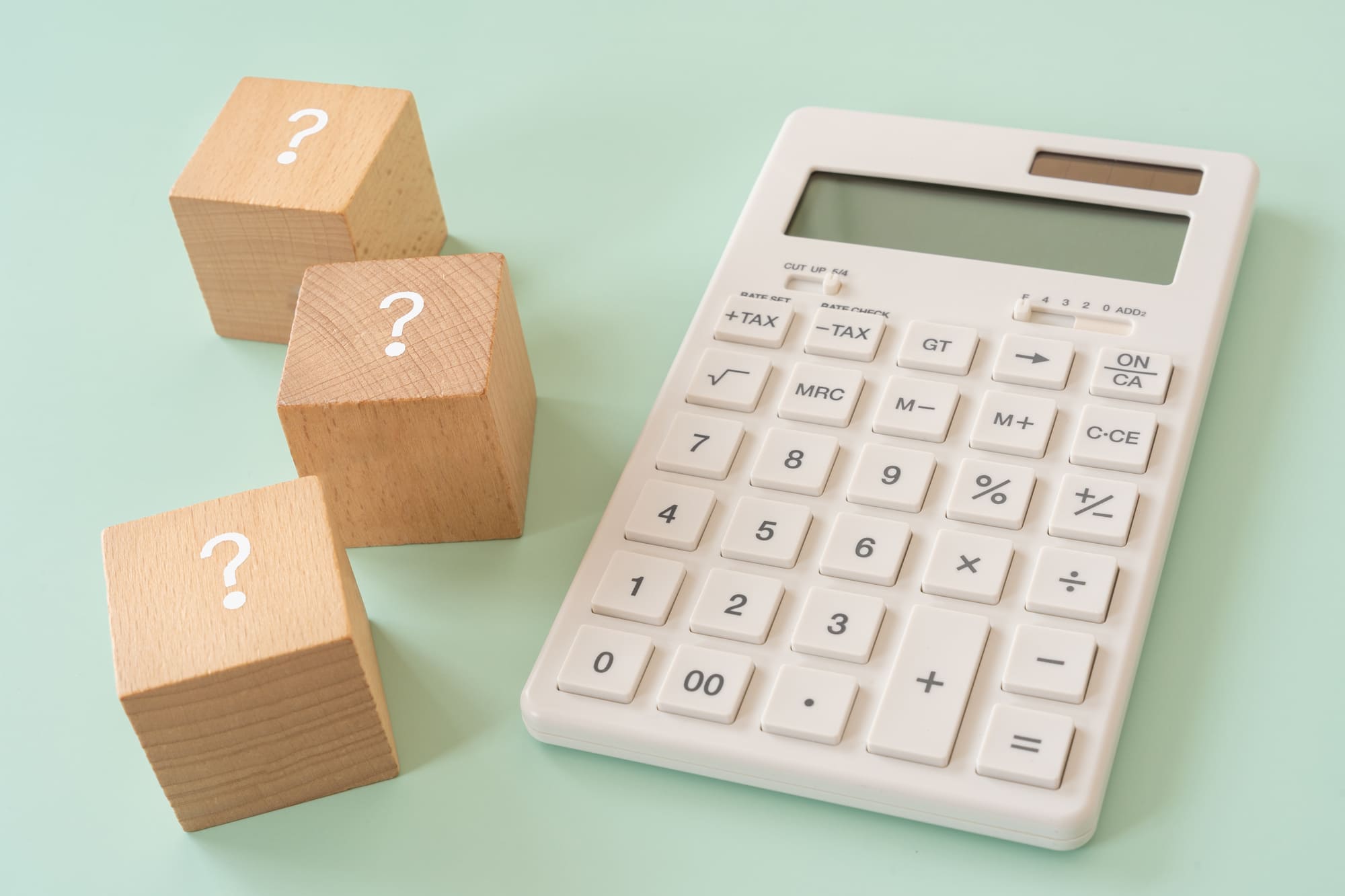
税務調査は法人だけでなく、確定申告をしている個人も調査の対象となります。実際に税務調査を受けた場合、支払うこととなる追徴課税はどのくらいになるのでしょうか。 この記事では、個人が税務調査の追徴課税の平均額はいくらになるのか、追徴課税となりやすい事例や、追徴課税となってしまった場合の対処法について解説しています。
税務調査の追徴課税で支払う平均額は?
税務調査で支払うこととなった追徴課税の平均額はいくらなのか、国税庁が発表している令和4事務年度の調査実績から解説します。所得税1件あたりの平均追徴額は約219万円
令和5年11月に国税庁から発表された「令和4事務年度・所得税及び消費税調査等の状況」によると、令和4事務年度の1件あたりの調査による追徴課税は約219万円となっていました。前年度の平均額256万円の85.5%となったものの、調査件数自体は前年比約1.5倍と、増加傾向となっています。 また、個人の消費税の税務調査による追徴課税の平均額は132万円となっており、所得税と合わせた場合、税務調査1件あたり平均約351万円が追徴されていることがわかります。税務調査になりやすい職種
税務調査はすべての業種が調査対象となりますが、過去の統計から税務調査で多額の不正や申告漏れなどが発覚しやすいとみなされる業種については、他の業種よりも積極的に税務調査が行われています。 令和4事務年度における税務調査において、1件あたりの申告漏れ所得金額が大きかった業種としては ・経営コンサルタント ・くず金卸売業 ・ブリーダー ・焼肉 ・タイル工事 が上位5業種として挙げられていました。 このほかにも、過去申告漏れの所得税額が大きい業種としてはバーやキャバクラ、風俗店などの水商売、システムエンジニア、冷暖房設備工事業などが挙げられます。 なお、令和4事務年度の実地調査による追徴課税額は1,015億円、簡易な接触(自発的な申告の見直しなどを電話や書面で進める調査)による追徴税額は353億円となっており、合計1,368億円と過去最高額を更新しています。 参照先: 国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」税務調査で追徴課税となった例を紹介
税務調査で追徴課税となりやすい例について見ていきましょう。業種
クラブやキャバクラの従業員や、建設業を営むいわゆる「一人親方」、プログラマーなどの個人事業主の中には、確定申告自体をしていない無申告者も多く、追徴額も大きくなりがちです。 また、近年ではインターネットを利用したシェアリングエコノミービジネスや、仮想通貨(暗号資産)による売却益などの申告漏れから多額の追徴課税が発生するケースも増えてきています。売上
売上において税務調査で指摘されやすいポイントとしては、当期の売上として処理するところを来期の売上としてしまう「期ズレ」が挙げられます。 例えば、12月に発注を受けて同月中に納品した場合、売上を計上するのは原則として納品した日付となります。 実際の入金は翌年の1月であった場合でも、12月中に売上を計上し、入金があるまでは売掛金として処理する必要があります。 もし翌年の1月に入金されたタイミングで売上を計上した場合、この取引については申告漏れであるとみなされる可能性があるのです。 期ズレ以外に、本来計上するべき売上が漏れていたり、計上した金額が少なかったりする場合にも、税務調査で発覚すれば過少申告として指摘されることとなるでしょう。利益
売上は適正に計上していても、経費の水増しなどで利益が少ないように申告している場合は、これも追徴課税の対象となります。 経費を証明するレシートや領収書がない場合や、経費とは関係ない支払いを経費として計上している場合、仕入先などと共謀して不正な領収書を入手、計上した場合なども、税務調査で指摘を受けやすいでしょう。 このほかにも ・架空のタイムカードによる人件費の水増し ・在庫品の計上漏れ ・使途不明な旅費交通費 ・私的利用が疑われる接待交際費や備品購入費 なども税務調査で見つかりやすく、追徴課税の対象となりやすいものです。自分では正しく計上しているつもりでも、プロや専門家が見れば間違っている、といったケースも少なくありません。消費税の税務調査にも注意が必要
インボイス制度の導入により、中小規模の個人事業主も課税事業者となったケースが増えています。 軽減税率の計算ミスや計上漏れに加え、海外からのアプリダウンロードなど、国境を越えた役務の提供に係る消費税(クロスボーダー消費税)の計上漏れなど、消費税の税務調査にも注意が必要です。個人が税務調査の追徴課税に対処する方法
税務調査の追徴課税に個人で対処するには、どのような方法があるのかについて解説します。個人でも税務調査対象となる可能性はある
「個人の自営業には税務調査は入らない」「何年も申告しているが税務調査になったことがない」というケースもある一方で、中小規模の個人事業主でも税務調査の対象となり、重い追徴課税を受けるケースも少なくありません。 税務調査を受けやすい業種はもちろん、その他の業種に従事している個人であっても、税務調査の対象となる可能性は十分にあります。 いつ調査を受けても安心できるように、日頃から適正な申告と納税を行い、過去の申告内容についても見直すことが大切です。無申告は放置せず早めの申告を
税務調査で追徴課税となるケースの中でも、無申告によるペナルティは大きくなりがちです。前年度だけでなく、過去の無申告についても遡って指摘を受けるだけでなく、延滞税や無申告加算税、重加算税などの加算により、自主的に納税するよりも追徴課税が多額となってしまいます。 無申告は取引先への税務調査や第三者によるタレコミのほか、税務署が持っている独自のルートからも発覚することがあるため、無申告は放置せず早めに申告、納税を行うようにしましょう。税務調査による追徴課税への対応が不安な場合は税理士へ相談を
税務調査で追徴課税となるケースは、よくある事例以外にも個人や事業の状況によって様々なケースが考えられます。もしかしたら、過去の申告内容において自分では正しいと思い込んでいるミスなどが含まれている可能性もあります。税務調査の可能性や追徴課税への対応について不安がある場合は、個人への税務調査対応実績などに明るい専門家へ相談するのがおすすめです。 税理士法人松本では、売上の規模や業種に関わらず、税務調査や追徴課税に関するお悩みに初回無料で相談対応をしています。専門家の目線とお客様の目線のバランスを大切に、誠実にお話を伺いケースごとに最適なサポートが可能です。無申告状態についてもご相談に対応していますので、不安や悩みは一人で抱えず、メールフォームやお電話にてお気軽にご相談ください。まとめ
税務調査では法人はもちろん、個人の申告内容も調査の対象としています。税務調査による個人1件あたりの追徴課税の平均額はあくまでも平均であり、もっと少ない場合でも税務調査の上、追徴課税されるケースもゼロではありません。 日頃から適正な申告、納税を心がけるのはもちろん、過去の申告内容をプロにチェックしてもらうか、税務調査や追徴課税について税理士へ対応を相談するなどして、曖昧な点や不安な点はクリアにして事業へ注力できるようにしましょう。免責事項 当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務調査で追徴課税が払えない!どうなるのか対処法を解説

税務調査で申告漏れやミスなどが発覚した場合、追徴課税の対象となります。この追徴課税が支払えない場合はどうなってしまうのでしょうか。 この記事では、税務調査で追徴課税が払えない場合はどうなるのかに加え、実際にどのような事例で追徴課税となるのか、払えない場合の対処法などについてわかりやすく解説しています。
税務調査で追徴課税が払えない場合はどうなる?
税務調査によって追徴課税となった税金が払えない場合はどうなってしまうのかについて解説します。追徴課税の支払いを免れることはできない
結論から言うと、追徴課税の支払いを免れることはできません。「追徴課税が払えないから」と言って放置していると、最悪のケースでは財産の差し押さえに合う可能性もあるのです。 追徴課税を期日までに支払わないと「滞納」と呼ばれる状態になります。支払いの滞納を続けていると、税務署から督促状が届き始めます。督促状が届いても無視を続けた場合、税務署は差し押さえ可能な財産があるかの調査に入り、「催告書」と呼ばれる差し押さえする旨の通告書が送られた後に、財産が差し押さえられることとなります。 差し押さえられる財産には ・預貯金、給与 ・売掛金、有価証券、保険金などの金融資産 ・土地、建物や家屋などの不動産 ・自動車、高級装飾品などの動産 などが挙げられます。 不動産や動産などが差し押さえられた場合、競売によって安価に売却されるため、実際の価値よりも低い価格で処分されてしまいます。 また、追徴課税の支払いを滞納すればするほど、7.9~14.6%の延滞税が発生し、支払いはより困難になってしまうでしょう。追徴課税は自己破産しても免責にならない?
「追徴課税以外にも支払えない債務があるから、自己破産すれば支払いをゼロにできるのでは」と考えたくなりますが、追徴課税を含む税金の支払いは、自己破産しても免責にすることができない点も注意が必要です。 自己破産は、クレジットカードの支払いや消費者金融からの借金、ローンの返済などを免責にすることができる手続きです。しかし、追徴課税を含む所得税や住民税などの税金は、自己破産をしても免責にできない「非免責債権」であることが法律で定められています(破産法253条第1項)。 自己破産すると他の支払いを免責にできても、一定期間はブラックリスト入りすることとなるため、新たな借金やローンを組むことができなくなってしまいます。借り入れができないことに加えて多額の追徴課税の支払い義務は残るため、更に苦しい状況に陥る可能性があるため注意が必要です。税務調査で追徴課税となる事例
所得税や法人税の税務調査で追徴課税となりやすい事例には、以下のようなケースが挙げられます。申告漏れ
本来申告するべき売上などの申告漏れが税務調査で発覚した場合です。申告漏れを指摘されやすい事例としては ・計算ミス、計上間違い ・前年度に計上するべき売上を次年度で計上していた(期ズレ) ・会社の資産を使用して得た個人的な収入を計上しなかった ・シェアリングサービスなどインターネットを利用した収益 などが挙げられます。 税務調査は所得税や法人税だけでなく、消費税や相続税、印紙税などにおいても申告漏れを疑われる可能性があるため注意が必要です。使途不明金
接待交際費の水増しや個人的な旅費などの経費計上について、証拠となる資料や説明が不充分な場合に経費と認められず、使途不明金とみなされてしまう場合です。 ・個人的な飲食代を接待費として計上した ・帰省した際の旅費を交通費に計上した ・自身の買い物を会社の備品や消耗品として計上した などは指摘を受けやすいでしょう。無申告
税務申告自体をしていない無申告の状態も、税務調査で発覚すれば追徴課税の対象となります。「申告していないから調べられることはないだろう」と思っていても、税務署では独自のルートやシステムを使い、無申告者をリストアップすることが可能です。 税務調査で申告漏れや経費の水増し、無申告などが判明した場合、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税などが追徴課税として課されることとなります。悪質な所得隠しや虚偽申告とみなされた場合、更に重い重加算税が課せられる場合もあるのです。追徴課税が払えない場合の対処法
追徴課税の支払いは、原則として法定の期日までに一括払いすることとなっています。しかし、どうしても支払えない場合には、状況に応じて以下のような対処法を取ることも可能です。救済措置を活用する
追徴課税が支払えない場合、事前に申請をすれば以下の猶予制度が活用できます。 ・納税の猶予:納税期間を延長し、支払いを待ってもらえる制度です。納税の猶予が認められた場合、1年間の分納が可能となり、猶予期間中の延滞税も減免されます。 ただし、納税の猶予を受けるためには相当の理由が必要となります。自然災害や病気、盗難、廃業などにより経済的に困窮している場合や、法定の納付期限が修正申告で税金が確定した日より1年以上遅い場合などに「猶予申請書」と「修正申告書」の両方を提出し申請することができます。 ・換価の猶予:既にある財産の差し押さえや、新たに差し押さえの予定となっている財産について差し押さえを待ってもらえる制度です。換価の猶予が認められた場合、1年間の分納が可能となり、猶予期間中の延滞税も減免されます。 換価の猶予を受けるためには、追徴課税以外の税金の滞納がなく、一括で税金を納付することによって事業の継続や生活が困難になると認められる場合に、法定納付期限の6ヶ月以内までに申請書を提出する必要があります。 いずれの猶予制度も原則として担保が必要となっていますが、要件によっては担保がなくても申請できる場合があります。法人の場合は自己破産でも免責にできる
個人が自己破産しても税金が免除されることはありませんが、法人が自己破産した場合、手続きが完了すると会社が消滅するため、法人税などの追徴課税は免責にすることができます。ただし、合同会社や合資会社などで無限責任を負っている場合や、代表者として納税保証書を発行している場合は支払い義務が残るため注意が必要です。対策に困ったら専門家へ相談を
長期にわたる申告漏れや無申告による脱税では、延滞税に加え無申告加算税や重加算税などがペナルティとして課せられるため、追徴額が多額となってしまうケースも少なくありません。追徴課税が払えずに困る前に適正な申告、納税をすることが大切ですが、現在払えずに困っている場合は、税務調査や追徴課税への対応実績が豊富な税理士へ早めに相談しましょう。 税理士法人松本では、税務調査の追徴課税への対応や支払いに困った場合の救済措置など、個別の状況を丁寧にヒアリングした上で最適なサポートのご提案が可能です。フリーダイヤルまたはお問合せフォームより、お気軽にご連絡ください。まとめ
税務調査で追徴課税が払えなくなってしまっても、基本的に支払いを免れることはなく、期日を過ぎても支払わずに督促状も無視していると、最悪の場合財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。 税務調査による追徴課税は、売上の計上漏れや記帳間違い、計算ミスや使途不明金などが発覚した場合はもちろん、無申告が発覚した場合にも発生します。法人の場合は自己破産で支払いを免責できる可能性がありますが、個人の場合は自己破産しても免責にできないため、適正な申告、納税や税理士などのプロによるサポートを早めに受けるようにしましょう。免責事項 当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
相談実績1,000件以上
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属
税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!
- 現在、税務調査が入っているので
困っている - 過去分からサポートしてくれる
税理士に依頼したい - 税務調査に強い税理士に変更したい
- 自分では対応できないので、
税理士に依頼したい
税務調査専門税理士法人松本